-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
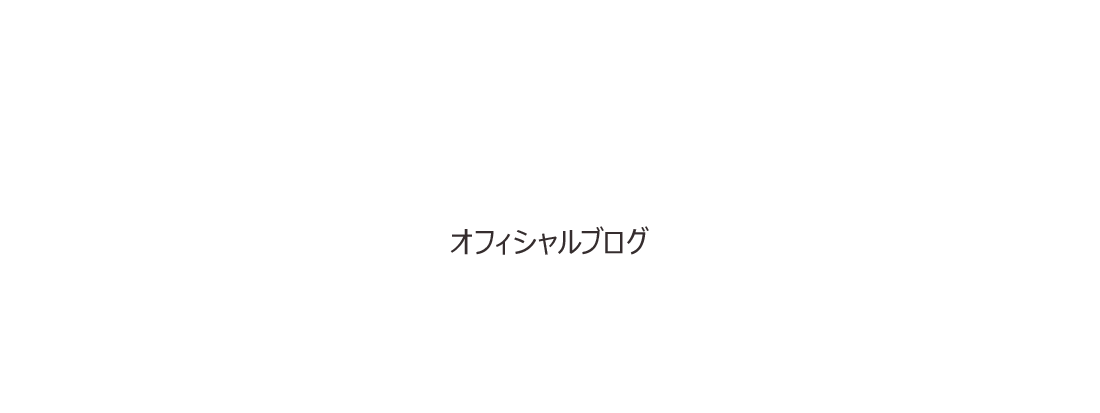
近年、アレルギー性疾患の患者が急増し、日本人の2人に1人が花粉症やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などに悩まされています。免疫が過剰に反応して起こるアレルギー性疾患は、腸内環境のバランスを整えると、症状が改善することが明らかになっています。
アレルギー疾患の代表例である花粉症は多くの日本人を悩ませています。花粉、ハウスダスト、ダニ、カビ、食べ物などのアレルゲンが侵入すると、マクロファージが異物を食べ情報をT細胞という免疫細胞に伝えます。ヘルパーT細胞が攻撃命令を出し、キラーT細胞が直接攻撃をしますが、その暴走を抑えるブレーキ役を制御性T細胞が担います。ヘルパーT細胞には2種類あり、マクロファージやキラーT細胞を元気にするIgG抗体作らせるを1型ヘルパーT細胞とIgE抗体を作らせる2型ヘルパーT細胞です。ストレスや食生活の乱れ、動物性脂肪や植物油(リノール酸)、タンパク質のとり過ぎ、生活環境など複合的な要因によってTh2細胞の力が強くなると、アレルギー体質に陥ります。 制御性T細胞の働きをコントロールして、アレルギーを引き起こすアレルゲンに反応するTh2細胞の働きを抑えることができれば、アレルギーを予防したり、症状を軽減できると期待されています。制御性T細胞は、腸内細菌による発酵によって腸管内で作り出せる短鎖脂肪酸の1種「酪酸」の作用で、大腸の中で生み出されています。短鎖脂肪酸は、腸の粘膜のエネルギー源としても利用されており、ミネラルの吸収、肝臓でのコレステロール合成抑制、腸管のバリア機能を高めるなど健康を維持する上で重要な役割を担っています。乳酸菌、オリゴ糖、シソ、オメガ3系脂肪酸などに抗アレルギー作用があることが報告されています。
日常生活の中でTh1とTh2のバランスを整えたり、制御性T細胞を増やすには、腸内細菌の活動を活発にすることが有効な方法になります。そのためには野菜や海藻類、納豆、味噌などの発酵食品を積極的に食べることが重要です。また食事で十分に摂れない場合に、サプリメントを日常の食生活に取り入れていくこともおすすめです。Th1とTh2のバランス改善、制御性T細胞の増加、短鎖脂肪酸の産生増加が確認されているものをご紹介します。
●乳酸菌を摂れるサプリメント(死んだ乳酸菌の方が、生きた乳酸菌より免疫力が3倍高いことが明らかになっています。)
・乳酸菌&カテキン(3024円) 腸内を殺菌するカテキンを含有。
●オリゴ糖を摂れるサプリメント(オリゴ糖は体内の乳酸菌を増やす腸内の土壌を作るのに働きます。本来善玉菌は体内で産生する方が腸に根付きやすいです。オリゴ糖を摂取して善玉菌を増やす土壌づくりをしましょう。)
・グリーン末(5184円) 大麦若葉などの食物繊維とフラクトオリゴ糖などを含有します。水や牛乳に混ぜる粉末タイプで抹茶の味が心地よいです。
・クオリコウカ(8640円) 北海道で摂れた天然の野菜60種類を発酵させて液体にしたもの。短さ脂肪酸も含み腸内環境を改善し、免疫力アップや病気の予防にもなります。
●オメガ3含有のサプリメント(現代の食事の中ではオメガ6の油を摂りがちですが、過剰に摂取することでアレルギーの原因になります。意図的にオメガ3含有の食品を摂取してバランスを整えましょう。)
・シーアルパ30(5832円) EPAとDHAを多く含有しその割には価格も抑えられておりお得な商品です。魚の油の専門のメーカーが作っています。
・オメガLIFE3-6-9 バランスよく油を摂取できるだけでなくスーパービタミンであるトコトリエノールなども含有し、抗酸化作用や発毛促進などの効果も期待できます。
・ビルベリー&DHA(6264円) DHAだけでなく目に良いビルベリーを含有、目と脳の両方に働きます。記憶力改善や視力向上など現代人に多い目と脳の悩みを解決します。
その他、紅芝泉、まんじゅのしずく、アクティブレイン、ヤツメウナギ肝の油などの商品があります。また、花粉症などのアレルギー性鼻炎に対応した眠気の少ない鼻炎薬や漢方薬なども取り揃えております。是非、お店にご来店頂きご相談下さい。
新月の日はデトックス効果が最も高く、やせやすい!満月の日は栄養の吸収力が高く、太りやすい!
新月の日と満月の日の夜だけ食事を抜いて酵素を飲むダイエット法があります。
新月の日は解毒、排泄、洗浄、発汗、発散といった体にいらないものを外へ出す働き、「デトックス作用」が最も高くなります。つまり最もやせやすい日なのです。
一方、満月の日は内に入れる働き、つまり消化や吸収、補給、修復、再生、充電、休養といったエネルギーを蓄えたり、取り込んだりする働きが最も高くなります。最も太りやすい日です。
新月の日と萬月の日だけでもいいので夕食を抜くとよいです。
月2回の夕食抜きでも、「チリも積もれば山となる」で、年間で24食、合計8日間の断食をしたことになります。
月にたった2食の夕食抜き断食であれば、だれでも実践しやすいのではないでしょうか?
月と太陽、地球が一直線に並ぶとエネルギーが高まる!
日本人は昔から日々、月を意識しながら暮らしてきました。日本人が生活の中で長く使用してきた旧暦では、新月の日を1日とするので、満月は15日あたりになります。人々は旧暦を使うことで、自然に月の満ち欠けを知ることができました。この旧歴で月を感じながら、大自然と調和した生活をしてきたのです。
「腎」、「肝」、「腸」、「脳」のように、人間の内臓を表す漢字には「月」がついていますが、このことからも昔の人は体と月には密接な関係があると知っていたのでしょう。
形をもたない柔らかな物質である水は、月の引力の影響を強く受けます。
月と向かい合っている海面は、月の引力に強く引かれ、大きく盛り上がるため、水位が上がります。月の引力によって潮の満ち引きは起きるのです。
私たち人間の体の約70%は水ですが、私たちの体内の水も月の引力の影響を受けています。
満月と新月の日は、ともに引力が強くなるため、体内に内在する力を引き上げ活性化するのです。
また、「太陽ー地球ー月」の順に直線状に並ぶのが満月で、「太陽ー月ー地球」の順に並ぶのが新月なのですが、このような位置になる時に引力が強まり、地球上の動物や植物の生命力は活性化されます。
何も食べない断食はよくない!酵素を飲みながら断食しよう!
何も食べない断食はいろいろな問題を起こすことが考えられます。一番の問題は、飢餓感を無理やり抑えることで、抑圧された感情がストレスとなり、交感神経が過度に緊張することです。
そして、抑圧されたストレスが断食終了後に爆発して、過食を引き起こしたり、甘いものを異常に欲するリバウンドを招いたりしてしまう可能性があります。
また、血液中に糖分切れが起こると、アドレナリンが過度に分泌して、イライラしたり、怒りっぽくなったり、逆に何もしたくないという無気力状態を引き起こしたりする低血糖を招くこともあるのです。
このような状態をまねかないためには、栄養をしっかり取り入れながらの酵素断食がおすすめです。酵素飲料を飲みながら断食を行うのです。
酵素を飲みながらの断食で、代謝酵素をより一層増やせる!
私たちの体内には3000種類ともいわれる膨大な数の酵素があり、日々の新陳代謝を担っています。そのうちの80%が消化に使われる「消化酵素」で、残りの20%が体の修復や再生、脂肪の燃焼に使われる「代謝酵素」です。
断食をすると、消化しなくていいので、消化に使われるはずだった酵素を代謝のほうに回すことができます。つまり、断食をすると、代謝を促進し、体の修復・再生や脂肪の燃焼や解毒が促進することができるわけなのです。
しかも、酵素を補いながら断食すると、より一層、代謝酵素を増やすことができます。
当店では多種の酵素飲料を取り揃えております。お客様のお好みに合わせて、適切な酵素飲料をお買い求めください。店頭にてお待ちしています!!
「ぢ」は・・・
①肝臓の疲れ
②胃腸の弱り
③下痢または便秘
④身体の冷え、疲れ
⑤妊娠
などが原因となって、肛門部の血液循環が悪くなり、うっ血(血が停滞)することにより、血管が腫れてイボになったり、腫れたところが破れて出血したりするものです。
また、切れ痔の場合は、血液循環が悪いがために皮膚が弱くなってしまい、切れやすくなり起こります。したがって、外から軟膏を塗ったり座薬や注入軟膏を挿入しても一時的にはおさまりますが、根本的には治りません。
ぢの正しい治療法
まず第一に「内臓の疲れをとり肝臓や胃腸の働きをよくするとともに、血流を改善することが大切です。レオピンは内臓の働きをよくし、ぢを起こす原因を取ってくれますので、治療を早めるとともに、飲み続ければぢの予防、再発防止になります。
そのうえでそれぞれのぢの症状に合った漢方薬を併用してください。
ぢはお尻の病気ではありません。肝臓や胃腸の疲れが間接的に(最も弱い)お尻に出ているだけなのです。不養生を注意し、内臓の調子を整えておくことが第一です。
ぢの養生法
1,排便習慣
①便意がなくても、朝食後決まった時間にトイレに行く
朝食後が一番便が出やすい。朝起きてすぐに便をする人は冷えや水分摂りすぎの人。
朝、冷たい水を飲むとよいと言われているが、冷たくなほうがよい。
②ウォシュレットの刺激で出すのも一時的には構わないが、それに頼らない。
③トイレに長居しない。最初の排便で80%は出ている。
ぢの人の便はベトッとしている。スキッと一度に出ない残便感がある。
④排便後はウォシュレットを使用し、紙で強く拭かない。
2、食養生
①水分を控える。
便が硬いから水を飲んだ方がいいと言うのは真っ赤なウソ。
実際に便を柔らかくするのは、
・食物繊維の中に含まれる水→だから食物繊維はしっかり摂る。
・胆汁
・血虚や陰虚の人は硬くなりやすいので陰分を補う。
②よく噛んで食べる。
ぢは腸が関わる病気なので食事はとても大事。
③香辛料・アルコール・糖分・冷飲食・もち米を控える。
香辛料→お尻がヒリヒリする。灼熱感。
アルコール→肝臓を弱める。
糖分→最終的には、水+二酸化炭素となるので、水分の摂りすぎになってしまう。
もち米→血液がもちもちする。患部に熱をもたせる。
④食物繊維(緑黄色野菜・根菜・海藻類)を多く食べる。
グリーン末はぢにとても良い。便通もよくなる。
3,運動
①肛門締め運動をする 肛門周りの血流も良くなり、腸の血流もよくなる。
②半身浴の励行(肛門周囲膿瘍時は禁止)
ぢ根本治療のアイテム
根本治療はコレ! レオピンシリーズ
ぢはお尻の病気ではありません。ぢの原因となる内臓の疲れをとってくれるレオピンシリーズで再発予防と根本治療をおすすめします。
粘膜を丈夫にする! カルシウム
カルシウムは皮膚や粘膜を丈夫にし、炎症を起こしにくい体をつくります。校門部の粘膜の抵抗力を上げるのもカルシウムの仕事です。
血行を良くする! ビタミンE
ぢは皮膚の冷えや疲れによって肛門部の血管がうっ血し、肛門に負担をかけてな病気です。血行を良くするビタミンEも強い味方です。
ぢの傷み・出血によく効きます 生田七
田七は、弱った肝臓の働きを高めてくれるだけでなく、止血・痛み止めの特効薬でもあります。予防と治療を兼ね備えた生薬です。
排便ごとの消毒は絶対に必要です レブメントFN
便には大腸菌などが多く含まれています。怪我をしたら消毒するように、お尻もまず消毒薬で清潔にしてから薬をつけることが大事です。
症状の緩和には外用薬で! 座薬・軟膏
痛みや出血がひどい場合は早く症状をとることも必要です。坐薬や軟膏は症状に合ったお薬と効果的な使用方法でご使用ください。
症状に合わせてぢの内服薬を! パイゾールS、K
出血のひどい場合、炎症のひどい場合にはぢの内服薬もおススメです。また、あなたに合った漢方薬をおススメいたしますのでお尋ねください。
便秘の解消も大切です! 腸内環境改善サプリ
ぢには、便秘や下痢は禁物です。症状をとると同時に快便を心がけないといけません。不足する栄養素を補い、腸内環境を整えましょう。
冷えは大敵!! カイロ、あったか靴下
身体の外からの冷えも大敵です。身体を冷やさないようにカイロや靴下、あったか下着などを利用しましょう。
ご相談は店頭にてお願いいたします!!
花粉の季節到来で鼻づまりを訴える方も増えてきました。
鼻づまりといっても原因や症状はそれぞれ違いますので、ご案内する薬もやはり違ってきます。
よこぜきドラッグでは、それぞれの症状に合わせた薬を取り揃えております。
・アレルギー性鼻炎
・後鼻漏
・蓄膿症
・慢性鼻炎
鼻炎は色んな種類の薬があって、選ぶのも難しいです。
お悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。
普段の生活スタイルやご体調、鼻水の状態などを伺いながらご提案をさせていただきます。
最後に、ご自身で今すぐ出来る鼻づまりに効果的なツボを1つお伝えします。
「迎香(ゲイコウ)」というツボです。
その名の通り、香りを迎えられるよう通りを良くしてくれます。
左右の小鼻のくぼみに位置します。
圧力は気持ちいいと感じる程度に。
押す時間は3秒。
これを5回繰り返してみてください。
少しでも気持ちよく素敵な春が迎えられますように。
2023年1月は日本列島が最強寒波に見舞われましたね。まだ寒さは続きますが暦の上では2月4日頃が立春となります。
人間の身体もゆっくりと春への準備を始める頃です。
東洋医学では「冬は腎の働きを、春は肝の働きを補うと良い」といわれています。
この時期は腎と肝の両方を養生しながら過ごしていきたいものです。
(ここでなぜ養生が必要なのか少しお話しします。
季節ごとに体調を崩すのは、前の季節にきちんと養生ができていなかったという証拠。ですので、先を見越して養生していくことがとても大切なんです。)
~腎と肝、ダブルの養生法~
・寒さを我慢しない
…くしゃみ、さらさら鼻水が出た時点で身体が「温め方が足りません」と言っているサインです。もう一枚上着を足す、カイロの数を増やすなど対策を講じる必要があります。
・外のウォーキングより室内の筋トレを
…腎と足腰は密接な関係にあります。下半身筋トレは体温も上げられ、免疫力向上にもなります。補腎に最適です。
・ゆったりノビノビ出来る時間を大切に
…休むのが下手と言われる日本人。「休むのも仕事」とスケジュールに組み込むことも手です。
・23時には入眠出来るとベストです。
…身体のガソリン=血液が、肝に貯蔵される営業時間に間に合うからです。
血液が足らなければ、身体は疲れやすいままです。
もしぐっすり眠れないなどございましたら、睡眠薬ではないサプリメントや漢方薬でじっくり向き合って改善していきませんか。
お気軽にご相談ください。
~食養生について~
・根菜類は身体を温めてくれるので、この時期の鍋や煮物は理に叶っています。
・冷たい飲食物や砂糖は冷えの元です。控えめに。
・黒い食材を食べましょう。黒ごま、黒豆、こんぶなど。
・香りある食材を少しずつ増やしていきましょう。梅、ねぎ、ニラ、セロリ、セリ。胃腸虚弱や貧血以外の人には緑茶も良いです。
熟成にんにくのレオピンはこの時期にもとってもおすすめです。
何を行うにも身体のベース作りが基本です。
・海外旅行に行きたくても、元気がなければ楽しめません。
・ダイエットしても、身体にその元気がなければ痩せにくいです。
・筋トレしても筋肉がつきにくいです。
逆に身体を壊してしまう方も多くいます。
養生と合わせてよこぜきドラッグをご利用いただければ幸いです。
●日本人の睡眠の質が低下している
ヒトは一生のうち約3分の1は眠っています。また、ヒトの脳の重さは約1.3㎏、体重の2%ですが、エネルギー消費量は体全体の18%です。脳がいかに活発に働いているかがわかります。この脳の疲労を回復するために必要なのが睡眠です。世界的に見て睡眠時間が特に短いのが日本の有職女性です。しかし、平成27年以降に睡眠時間の減少に歯止めがかかった一方で、睡眠に満足していない方が多くいることがわかりました。睡眠時間を増やすだけでなく、質の良い睡眠をとるこが、私たちの健康にとって重要です。
●2つの眠り
レム睡眠(眼球が素早く動きます) 体は眠っていますが、大脳は覚醒時に近い状態で活動しています。そのため、夢をみることが多くなります。また、その日の出来事や勉強したことなど、記憶の固定や消去など情報整理も行っています。
ノンレム睡眠 4つの段階で睡眠の深さが変化し、大脳が眠っている状態です。免疫機能や体の修復のためのホルモン分泌も行われます。寝返りを行うことで、滞りがちな血行を良くし体を回復させます。
ノンレム睡眠からレム睡眠になるサイクルを1周期として、平均90分サイクルが繰り返されます。加齢とともに深いノンレム睡眠が減少し、高齢者では中途覚醒になります。
●睡眠中に分泌されるホルモン
・疲労回復に作用する成長ホルモン 眠りに入って45分後あたり、最も眠りの深いノンレム睡眠のときに多く分泌される。
・身体を目覚めさせるコルチゾール 副腎から分泌されるステロイドホルモンの一種。明け方の起床時前に分泌量増加、覚醒に必要なホルモン。
・健康的な眠りを導くメラトニン セロトニンから作られる。朝日を浴びた約15時間後、夜間になるとさかんに分泌される。
●睡眠と5つの元気
・睡眠と内臓元気
睡眠時間が短いと肥満になりやすいことが報告されています。また、インシュリンの働きを低下させたり、食欲を増進させるホルモンの分泌を増加させるなどして肥満や過食を助長して、糖尿病を悪化させることが分かってきました
・睡眠と血管元気
通常睡眠と短時間睡眠の日、それぞれの血圧を測定したところ、短時間睡眠の日では血圧が高くなりました。
・睡眠と神経元気
認知症が睡眠の問題を引き起こすだけでなく、睡眠の問題が認知症のリスクを高めます。
・睡眠と免役元気
睡眠時間が短いほど風邪症状が出やすいことがわかっています。メラトニンは快眠を促しますが、さらにその刺激により腫瘍細胞やウイルス感染細胞を除去する細胞の働きが活性化します。
・睡眠と骨元気
睡眠時無呼吸症候群患者の骨粗鬆症罹患リスクが2.7倍高かった。65歳以上ではリスクは5.8倍に、女性では8.7倍になりました。
(睡眠薬の 使用上の注意)
過剰服用に注意 持ち越しふらつき 寝る前に飲む お酒と一緒に飲まない
●良質な睡眠を手に入れる生活習慣(養生法)
・食事と運動
快眠におすすめの食べ物 睡眠物質メラトニンの材料トリプトファンを摂る
~バナナ、乳製品、卵、ゴマ・ナッツ、アボガド、鰹節など
・快眠ストレッチ ~睡眠前のストレッチ
① 座って両足を伸ばした姿勢になる。手を組んで前に出すようにして背中をゆっくり伸ばす。
② 後で腕を組んで伸ばすようにして胸をゆっくり張る。
●睡眠力を上げるために試して欲しい習慣
① 目が覚めたら日光を取り入れて、活動スイッチオン
② 朝食は心と体の目覚めに重要
③ 毎日同じ時刻に起床
④ 昼寝をするなら、15時までの20~30分間
⑤ 軽い運動を習慣に
⑥ お茶やコーヒーは就寝前4時間、喫煙は就寝前1時間は避ける
⑦ 食事は軽め位に、就寝2時間前までに済ます
⑧ 終身1~2時間前にぬるめのお風呂
⑨ 部屋の照明は明るすぎず、就寝前の携帯、パソコンは避ける
⑩ 睡眠薬代わりの寝酒はやめる
⑪ 眠くなってから寝床に入る
⑫ 睡眠中の激しいいびきや、むすむずに注意
●眠りにおすすめの成分
・ラフマ 睡眠の質の向上に役立ちます。1週間の摂取期間でノンレム睡眠時間の割合を増加させ、睡眠の質(眠りの深さ)を向上させた。8日間の摂取で、起床時の睡眠に対する満足度を向上させた。
・GABA 一時的に落ち込んだ気分を前向き(積極的な気分、いきいきした気分、やる気9する機能があります。肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康をまもることを助ける機能があります。
・HMBカルシウム 深い睡眠時に分泌される成長ホルモンが筋肉を強化させるのに役立ちます。
睡眠についてのご相談は店頭で!!
●疲労とは
「疲労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減衰状態である」と定義されています。疲労は、心身の過負荷により生じた活動の能力の低下のことを言い、思考能力の低下や、刺激に対する反応の低下、注意力の低下、動作緩慢、行動力の低下、目のかすみ、頭痛、肩こり、腰痛などがみられます。
疲労は大きく分けて末梢性疲労、中枢性疲労の2種類があり、病気によって引き起こされる病的疲労などがあります。疲労を察知するのは脳であり、脳が危機を感じ取り体に不快感や倦怠感を与え、休むように警告します。末梢性、中枢性疲労は一時的なものであれば、ただちに休息や睡眠をとることで回復します。しかし休んで疲れが残る、睡眠時間は十分でも常に疲労感がある場合は、慢性疲労の可能性があります。病的疲労は病気によって末梢、中枢に感じる疲労であるため、病気にかからないように「予防」を心がけることが重要です。
●生活習慣
☆疲労回復に役立つ栄養素と食材
疲労を改善するには十分なエネルギーと、様々な食べ物からタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素をバランスよく摂る必要があります。食事はバランスよく食べるのが基本。エネルギーを効率よく産生する手助けをしてくれるような食材や抗酸化作用のある食材を取り入れましょう。
☆睡眠の質の向上に役立つ新商品“ 眠りエール“の登場
“眠りエール“ に含まれるラフマを摂ることで、ノンレム睡眠の割合を増加させ、睡眠の質(眠りの深さ)を向上させた。またGABAを含有し、肌の健康にもお役立ちできます。ぜひ、店頭にてご相談ください!!1日3カプセル服用 1か月分で5832円(半月分3000円から)
☆遅筋を鍛えるインターバル速歩のやり方
筋肉細胞には遅筋と速筋の2種類があり、遅筋には酸素を使いATPを生みだすミトコンドリアを多く含みます。遅筋を増やすことがミトコンドリアの増加を促し、疲れにくい体作りに繋がります
①視線は約25m先を見て背筋を伸ばした姿勢を保ちます。
②足はできるだけ大股を意識して踏み出し、踵から着地します。初めは1.2.3と数えて3歩目を大きく踏みだすようにします。肘は90度に曲げて腕を前後に大きく振ります。
③速歩のスピードは「ややきつい」と感じる程度で行います。
④「3分間の速足(さっさか歩き)と3分間のゆっくり歩き」を1セットとし、1日5セット以上、週4日以上を目標にします。
●痛みによって発症する症状
通常、どこかケガをしたり打撲したりすると痛みが現れます。例えば、ハサミで指を切ったら出血し痛みが現れます。痛みと出血により筋肉が興奮して身体が固くなります。身体の筋肉が固くなると血管を圧迫して血流が悪くなります。血流が悪くなると、各臓器に送る血液量が低下し、本来の臓器の作業を円滑にできなくなります。
●痛みと自律神経と田七人参の関係
痛みがストレスと感じられると視床下部が興奮し交感神経を活発にします。その結果、副腎髄質に働きかけ、カテコールアミンが分泌され血糖値や血圧を上昇させます。
痛みによって精神的に安定することは出来ません、身体の機能としては常に攻撃態勢になっています。田七人参のサポニンは自律神経に対して、効果が期待でき、特に鎮静サポニンが素晴らしい働きをしてくれます。
田七人参を摂取すると、痛み・ストレスからくる、自律神経の乱れを調整して、きっと明るく楽しい気分にしてくれるはずです。
●痛みと天気・・・
雨が降る前は何故痛いのか?
雨が降る前は何故調子が悪いのか?
長い間、痛みにさらされた古傷が痛む
気圧が下がると内耳が関知して、視床下部を通じて交感神経が亢進される。
ホルモン(ノルアドレナリン)が放出され、痛みを感じる神経を刺激する。
ノルアドレナリンは血管を収縮させてり、マクロファージや肥満細胞を活性化させ、ヒスタミンなどの物質を放出させ、痛みを感じる神経を刺激します。
副腎髄質にも働き、アドレナリンを分泌し痛み神経を刺激します。
●痛みと感情
イライラすると痛くなる・・・?
痛みが強く現れる 痒みも強く現れる
イライラすると身体はどうでしょうか?
身体が熱くなり汗をかいて興奮状態に陥ったことはないでしょうか?血液がスムーズに流れなくなり、血管は血液を流そうと収縮して血圧を上昇させ、いわゆる頭に血がカーッと昇った状態になります。
身体が熱くなると、痒み・痺れが起こる経験はありますよね。
ストレスを感じると視床下部を介して下垂体前葉からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を分泌して、副腎皮質に働きかけたり、交感神経を亢進させることで副腎髄質に働きかけます。
●痛くないはずの刺激が痛い
痛覚神経
炎症が続いたり神経が損傷を受けると、正常では痛みを感じない刺激でも痛みと感じることがある。
神経損傷時の痛み
神経線維が損傷を受けると痛みが生じる
神経再生時には痛みが現れる
脳の記憶
痛みを感じると、脳の働きによって痛みを回避しようとするシステムが働くのですが、その記憶により損傷もなく何もなくても痛いと感じることがある。
●痛み半本当に共感できるのか?
痛みは感覚でもあり、感情でもあります。
その人の置かれている状況で大きく変わります。
慢性的なストレスや障害があるときは、通常よりも痛くなる。
病気やケガにより正常な痛みの機序が保てなくなると、理解できないような痛みを訴える場合があります。
痛みは共感ができない症状ですから、痛みの負の連鎖が起こる前に適切な手当てが必要です。これくらい大丈夫・我慢すれば・いつもの痛みだからと放置すると知らない間に障害として積み重なっています。初期の段階から痛みを取る、血液を流すことを考えてみませんか?
●痛みは一言では語れない
急性痛と慢性痛がある
一次痛・・・鋭い痛みで場所がハッキリしている 田七人参が強い効果を発揮できます!
二次痛・・・鈍い痛みで場所が曖昧である 田七人参と漢方薬の併用をお勧めします!
炎症を伴う痛み 侵害受容性疼痛 程度にもよりますが田七人参の出番です!
身体各組織の損傷や炎症・腫瘍などの病変によって、痛覚受容体を含む傷害受容器が侵害刺激を受けたために起こる痛み。
神経の障害に伴う痛み 神経障害性疼痛 田七人参と漢方薬の併用!
組織の損傷や皮膚の症状が治っても神経が痛みを引き起こす痛み。
心理的な痛み 心因性疼痛 田七人参をお勧めしますがストレスから回避!
明らかな身体的な原因がなく、発生に心理社会的因子が関与している痛み
初期の段階での痛みは田七人参を飲用することで治療日数も短く、費用も少額で済みます。
●腸内を鍛え体も心も健康に!
腸内を元気にする「腸活」は、近年の健康のキーワードとなっています。朝日新聞によると、腸活で意識して取り組みたいことは?との質問で、69%の方が「免疫力を高める」と回答。腸内環境を整え、腸を鍛えることが免疫につながっていると意識されていることがわかります。
ヨーグルトを食べているだけで腸を元気にできるわけではなく、腸内を元気に鍛えるためには、多様な腸内細菌が住んでいることが必要です。腸内には約1千種類という腸内細菌が共生しており、多様な腸内細菌が腸内で過ごすためには、食物繊維やアミノ酸など、加えてEPA、DHAなどのオメガ3脂肪酸も大切な役割を果たしています。特に野菜や果物に含まれる成分は種類によって大きく異なり、腸内細菌の多様性を応援してくれます。また、発酵食品は、酵母や乳酸菌などにより食物を分解し、健康に役立つ成分を作り出してくれます。
反対に、腸年齢が老いる要因は、腸内細菌の多様性の低下です。原因として、高脂肪食、高単糖食などがあげられます。腸内細菌の力を借りずに消化吸収してしまうために、腸内細菌の力が弱まります。
●肥満を防ぐ腸内細菌がいる
「ダイエットしたいけど、なかなかできない」という人がいます。最近の研究では、腸内環境が肥満の原因になることが知られています。実は腸内の肥満の原因になる「肥満フローラ」を「やせフローラ」に変えることができることがわかってきました。東京農業大学の木村郁夫さんは、腸内細菌が作る「短鎖脂肪酸」という物質に注目しました。肥満は、脂肪細胞と呼ばれる細胞が内部に脂肪の粒を蓄え、肥大化することでおこります。この脂肪細胞の働きにブレーキをかけるのが短鎖脂肪酸です。また短鎖脂肪酸をつくる細菌たちは「食物繊維」をエサとして生きているため、食物繊維が不足すると腸内細菌が減り“肥満フローラ”になってしまいます。ダイエットしたい人は野菜を多めに食べれば、“肥満フローラ”を“やせフローラ”に変えていけます。
●短鎖脂肪酸には、糖尿病を直接的に改善する効果も!
糖尿病患者を対象に、朝晩2回プレバイオティクス薬を飲んでもらい、4週間後に糖尿病が改善していることが明らかになりました。薬を飲んだ人は食後のインスリンが出やすくなり、血糖値の上昇が抑えられることが確かめられました。短鎖脂肪酸には、“天然のやせ薬”としての効果だけでなく、糖尿病を直接的に改善する効果もあるのです。
腸から細菌の毒素が増えると万病のもとに!
糖尿病の患者は、腸内細菌の出す毒素であるLPSの濃度が高いことが報告されています。腸のバリア機能が衰えることで、腸内細菌の出す毒素が全身の血管を弱い炎症状態に導き、糖尿病の引き金になるとの仮説があります。どうして糖尿病患者の腸のバリア機能が低下したのでしょうか?腸内細菌が出す短鎖脂肪酸の一種である「酢酸」に腸のバリア機能を高める力があります。私たちの腸壁の細胞は、腸内細菌が出す「短鎖脂肪酸」をエネルギー源としています。腸内フローラのバランスが低下して、「短鎖脂肪酸」の生産量が減ると、腸の細胞が活力を失ってバリア機能が低下してしまうのです。腸のバリア機能を高めるには。短鎖脂肪酸を増やす「食物繊維」が多めの食生活をすればいいのです。動脈硬化やガンなどの原因も“漏れる腸”であり、腸内フローラが乱れて短鎖脂肪酸の生産量が減ったことにあることにあるということになります。
●当店お奨めの商品
食物繊維・・“グリ―ン末”には便秘の解消になる不溶性食物繊維と高血圧、糖尿病、高脂血症の改善になる水溶性食物繊維が1日分6g入っています。そのままでも、お湯などに溶かしても飲めます。よく混ぜて飲むことで十分な食物繊維を補えます。
アミノ酸・・当店おすすめの“キョーレオピンW、キョーレオピンネオ”には肝臓分解エキスが、“コンクレバン”には肝臓加水分解物が入っております。天然のアミノ酸を補給することで筋肉や血を作る原料になります。
EPA、DHA・・“ビルベリー&DHA”にはDHAが1日分として280㎎、“シーアルパ30”には1日分としてEPAが762㎎、DHAが362mg含まれています。
発酵食品・・大髙酵素の“クオリコウカ”は天然の発酵食品です。北海道産の野菜を50種類以上樽の中、長年ねかせて作っておられます。また沖縄の食物素材をつかった発酵飲料“まんじゅのしずく”も発酵食品です。
骨が弱るとこんなリスクが!!
骨折や背中が丸くなるなど心配です。特に骨折は運動能力が落ち、要介護や寝たきりになります。
また、骨密度が下がると骨が縮小しますが、顔の骨も例外でなく、たるみやしわの原因になります。
特に下あごの骨が縮小しやすく、口の周りに放射線状にシワができます。骨は見た目年齢も左右します。さらに、記憶力の低下、筋力の低下、免疫力の低下にも関係します。
年とともに減るカルシウム
40代を過ぎると急激にカルシウム量が減ります。女性に多いのは、骨の形成を促し骨の破壊を抑える働きをもつ女性ホルモンの分泌が、閉経を機に急激に減少し骨量も減少することです。できれば40代から骨が弱くならない様に予防に努めることが理想です。50代では転倒して骨折して気づく人も多く、その後は姿勢の悪さや身長が低くなります。60代になると背骨の圧迫骨折が急増します。これは1つ折れると2つ目の骨折も起こる可能性が倍増します。「骨折の連鎖」「ドミノ骨折」と呼びます。
40代から予防するのが理想ですが、60代以降では遅いのでしょうか?そんなことはなく、いくつになっても骨は丈夫にできます。骨は新陳代謝していて、正常なら5か月で生まれかわり、全身の骨が生まれかわるのは3年程度です。よい運動習慣、食生活、漢方やサプリを活用しましょう。
骨を丈夫にするためには?
① 骨に衝撃を与える運動をする!
骨に衝撃を与えると、骨量が増えます。骨センサーが骨への衝撃を感知して、骨を作るアクセル役のメッセージ物質を発します。ランニングや自転車運動をしている中年男性の骨量調査から、骨粗鬆症予備軍の人の割合が減少することが確認されています。そこまでできない場合にはウォーキングや次に紹介する「かかと落とし運動」をおすすめします、
1, まっすぐに立つ
足を揃えて立ち、手は自然にたらす。目線は前へ、脚は肩幅に開く。
2, つま先立ちになる
かかとを上げてつま先立ちになる。不安定な場合は、テーブルやイスにつかまっても良い。
3, ストンとかかとを落とす
足の力を抜き、かかとをストンと地面に落とす。かかとに少し響くような衝撃を感じる程度が良い。
② バランスの良い食事を心がける
骨づくりの鍵になる、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、マグネシウム、亜鉛、タンパク質などをバランスよくとりましょう。しかし食事だけでは十分にとれていない現状があります。とくにカルシウムはすべての年代において、実際の摂取量が推奨量を下回っています。食事でとれない栄養素を吸収の良い天然のカルシウム製剤などで補給しましょう。
③ 腎を強くしましょう!(補腎のすすめ)
東洋医学では、「腎」は骨と密接に関係しています。腎臓でビタミンDが活性化されることで、腸からのカルシウムの吸収が促進され骨が強くなります。漢方でいうところの骨を強くする「補腎薬」、例えばロクジョウ、イカリソウ、トシシなどがおすすめです。また骨密度の低下を防ぐ作用のある熟成ニンニク抽出液も含む“レオピンロイヤル”などもおすすめです。カルシウムなどの栄養素は胃腸から吸収されますが、それを元気にする働きもあります。
実は骨から若返り物質が出ています!
骨の役割は体を支えるだけではなく、全身の臓器に若さを呼び起こすメッセージ物質を送ります。
一見無口に思える「骨」が人体のネットワークを通じ、脳や筋肉など全身の臓器にメッセージを送り続けています。そのメッセージが途絶えると、老化現象も加速するそうです。高齢者の4~5人に一人が、大腿骨の骨折をきっかけに、1年以内に命を落とすというデータも出ています。
骨から出るメッセージ物質
オステオカルシン
・記憶力をアップします。
・精力をアップします。
・筋力をアップします。
オステオポンチン
・骨髄にある造血幹細胞を増やします。
・造血幹細胞が免疫細胞、赤血球、血小板に成長します。
人生百年時代!骨を守って元気で若々しく過ごしましょう!
骨密度測定会を11月24日(水)、25日 (木)に実施します!!
ぜひご自分の骨の状態を確認してみてください!!